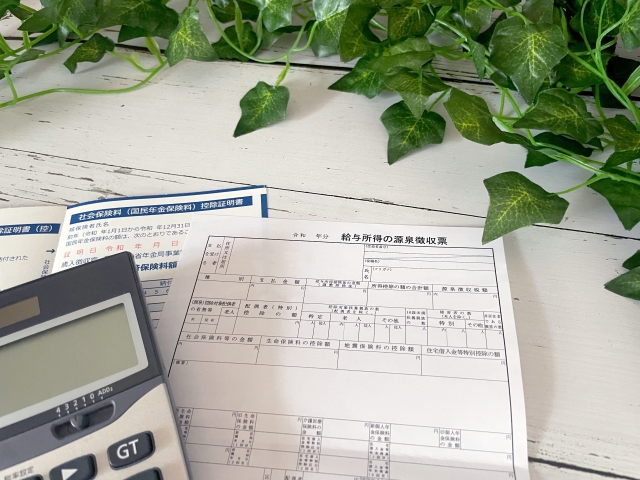この時期になると、順に保険料等の控除証明書が手元に届きだしていると思います。
会社員であれば年末調整に使用するために必要書類に記載して会社に提出するケースが多いですが、個人事業主は会社員ではないため扱い方が少し違います。
個人事業主は1月1日から12月31日までを1年としてカウントします。これは日常生活ともリンクしているのでイメージしやすいですね。
1年間の収入から経費を差し引いて所得を求め、そこからさらに所得控除を差し引き、課税対象となる所得を算出し、これを税務署に申告することを確定申告と呼んでいます。
前述のとおり、会社員(給与所得者)は勤務先が年末調整を行うため確定申告は不要なケースが大半ですが、自営業者は自分で申告手続きが必要となります。
この確定申告を行う際に、支払った生命保険料や社会保険料などの控除を受けるために添付する書類が、続々と手元に届き始めている控除証明書というわけです。
加入している保険等によって送付時期が異なりますので、届き漏れがないか、または紛失していないか確認する必要があります。※紛失の場合は再発行が可能なケースが多いです
ただし、国民健康保険、介護保険は控除証明書は発行されず、支払額のお知らせ等の名称で自治体から郵送されてきます。また多くの方が利用しているふるさと納税は、寄付をしてから後日自治体から郵送される流れとなっており、寄付した日付が基準になっているそうで送付時期はバラバラなようです。
確定申告書に所得控除の金額や内容の記入をし、控除証明書の添付を行うことで適用されますので、記入し忘れると当然適用されません。
ただし、更生の請求という手続きを行えば、遡って5年は申請忘れのリカバリーができるそうなので諦めずトライしてみてくださいね!
課税対象となる所得(課税所得)に税率をかけたものが納税額になりますので、所得控除の金額が大きければ大きいほど節税につながるという仕組みになっていますので、制度を正しく活用し、手元にお金が残るようしっかり管理したいですね!
【無料創業相談実施中!】
知識ゼロ、計画ゼロでも大丈夫!
あなただけの創業ストーリーを作っていきましょう♪
LINE、HPから無料創業相談のお申込みをお待ちしています!